費用の目安
※以下は代表的な業務に関する料金の例です。全て税込表記。
※その他税金と実費がかかる場合は事前にお伝えさせて頂きます。

1.不動産の登記関係
| 所有権移転(売買等) | ¥44,000〜 | 所有権移転登記とは、売買や贈与などで、不動産の所有者の名義が変更される時に行う登記のことを言います。 |
|---|---|---|
| 抵当権設定 | ¥38,500〜 | 抵当権設定登記は、事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをするため、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合に必要となる登記です。 |
| 抵当権抹消 | ¥17,600〜 | ローン等の支払いを完済しても、抵当権設定登記は自動的に抹消されません。 抵当権を抹消するための手続きをして、ようやく抹消されます。 |
| 不動産の相続 | ¥77,000〜 | 不動産の所有者が亡くなられた場合は、相続人の名義に変更します。 |
| 氏名・住所の変更 | ¥11,000~ | |
| 配偶者居住権設定 | ¥38,500〜 | 亡くなった方の配偶者が一定の要件のもと、居住建物を無償で使用等する権利を設定します。 |
| 建物表題登記 | ¥82,500〜 | 建物表題登記とは、建物を新築した時に最初に行う登記で、建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記簿の表題部に記録します。表題登記は、建物の完成後1カ月以内に手続きを行うよう不動産登記法で定められています。 |
| 建物表題部変更登記 | ¥44,000〜 | 登記されている建物の種類が変わったり、増築した場合に必要になります。 |
| 地目変更登記 | ¥38,500〜 | 地目とは、土地の用途による区分のことです。不動産登記法で23種類が定められています。地目に変更があった場合には、1ヶ月以内に変更の登記申請をしなければなりません。 |
| 建物滅失登記 | ¥38,500〜 | 建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。 |
| 合筆登記 | ¥44,000〜 | 合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいいます。但し、制限がありますのでご相談ください。 |
| 土地分筆登記 | ¥330,000〜 | 分筆(ぶんぴつ)とは、1筆(いっぴつ)の土地を分割して、複数の土地にすることをいいます。土地が分筆されれば分筆後の土地には新たな地番が付され、新たな登記記録が作成されます。 |
| 建物新築パック | ¥154,000 | 自宅や事務所の建物を新築する時、建物の表題登記から所有権保存登記、銀行のローンを使われるときはその抵当権の設定登記などの全ての登記手続きをお任せください。 |
※全て税込
2.測量・境界調査
| 簡易測量 | ¥77,000~ | 現況をTSを使い測量します。簡易な図面の作成まで行います。 |
|---|---|---|
| 境界確定測量 | ¥220,000〜 | 隣接者と立会いの下、測量を行い境界を確定していきます。 |
| 官民境界協定申請 | ¥132,000~ | 民地と市道・県道又は法定外道路・河川等との境界を確定したい場合に必要となります。 |
| 隣地境界調査 | ¥55,000〜 | 法務局や役所の資料等を収集し、境界の調査を行います。 |
| 法務局等資料調査 | ¥33,000~ |
※全て税込
3.各種許可申請
| 農地法3条許可申請 | ¥55,000〜 | 農地を、農地のまま売買、賃貸借などを行う場合、市区町村の農業委員会又は都道府県知事の許可が必要です。 |
|---|---|---|
| 農地法4条、5条許可申請 | ¥93,500〜 | 4条は、自分の所有する農地を自分が使用するために宅地、駐車場、資材置き場などに転用する場合、 5条は、農地の所有者と他者との間で所有権移転、賃貸借権などにより新たに権利を取得する者が転用する場合などに都道府県知事の許可が必要です。 |
| 農地法4条、5条届出 | ¥38,500〜 | 農地が、都市計画区域内で市街化区域内にある場合や、耕作事業者が2a未満の農業用施設(進入路、農業用水路、農業用倉庫、温室など)を設置する場合は、許可ではなく市町村の農業委員会へ届出をします。 |
| 非農地確認申請 | ¥55,000〜 | 地目が農地であるが、非農地化してから20年以上経過し、農地への復旧が困難な場合に行います。 |
| 建設業許可申請 | ¥110,000〜 | 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 |
| 建設業更新許可申請 | ¥55,000〜 | 許可を受けてから5年おきに更新許可をする必要があります。 |
| 建設業各種変更届 | ¥28,600〜 | 決算変更届、役員変更届等が起こった場合は提出期限内に変更届を提出する必要があります。 |
| 建設キャリアアップシステム登録 | ¥33,000〜 | 建設業に従事する事業者や技能者の登録を行います。 |
| 宅建業許可申請 | ¥110,000〜 | 宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。 宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいいます。 |
| 宅建業各種変更届 | ¥28,600〜 | 役員変更、宅建士変更等が起こった場合は提出期限内に変更届を提出する必要があります。 |
| 酒類販売免許申請 | ¥110,000〜 | 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要があります。 |
| 古物商許可申請 | ¥44,000〜 | 古物を売買・交換等する営業を行う場合、公安委員会の許可を受ける必要があります。 |
| 産業廃棄物収集運搬許可申請 | ¥110,000〜 | 産業廃棄物を排出業者から委託を受けて運搬等するためには予め許可を受ける必要があります。 |
| 道路使用許可・占用許可 | ¥55,000〜 | 道路において工事・作業をする場合や看板等を設置する場合に許可を受ける必要があります。 |
| 道路法24条申請 | ¥110,000〜 | 歩道の切下げ、床版設置等で道路工事を行う場合、道路管理者の承認を受ける必要があります。 |
| 道路位置指定申請 | 要相談 | 築造する道を建築基準法上の道路をして位置の指定を行う場合に必要となります。 |
| 開発許可申請 | 要相談 | 建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成等を行う場合は、都市計画法第29条の許可を受ける必要があります。 |
| 河川占用許可申請 | ¥88,000〜 | 河川に床版等を設置する場合、占用許可申請をする必要があります。 |
※全て税込
4.法人関係
| 会社設立サポート | ¥77,000〜 | 会社を設立する際には、「定款」を作成し、法務局に登記をすることが必要になります。 会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。 さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。 |
|---|---|---|
| 役員変更 | ¥33,000〜 | 役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任、死亡、解任した場合、また新たに就任された場合等に行う登記のことをいいます。 ※住所変更のみは¥22,000 |
| 本店移転 | ¥28,600〜 | 会社の本店を移転した場合、2週間以内に変更登記をしなければなりません。 |
| 目的変更 | ¥33,000〜 | 株主総会で定款を変更することにより目的の変更を行います。 |
| 定款変更サポート | ¥33,000〜 | 定款とは、会社の組織・運営・管理等を定めた会社の根本規則であり、一般的にはその規則を記載した書面等をいいます。会社の商号や目的等を変えたい時は、株主総会を開いて定款を変更します。 |
| 株主総会等議事録作成 | ¥16,500〜 | 株主総会では、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができます。(但し、取締役会設置会社を除く) その議事の経過と要領を記録したものを株主総会議事録といい、書面等で作成し保管しなければならない旨会社法に規定されています。 |
| 資本金の額の変更 | ¥33,000〜 | |
| 解散・清算決了 | ¥99,000〜 | 廃業する場合、解散の登記及び清算決了の登記をすることにより法人格を消滅させることが出来ます。 |
※全て税込
5.裁判所提出書類・訴訟代理
| 簡裁訴訟代理 | 着手金 ¥33,000 成功報酬:経済的利益の15% |
簡易裁判所で行う140万円以下の民事訴訟において代理致します。 |
|---|---|---|
| 訴外和解交渉代理 | 着手金 ¥33,000 成功報酬:経済的利益の15% |
|
| 裁判書類(訴状等)作成 | ¥44,000〜 | 裁判を行う際の書類作成を行います。 |
| 相続放棄手続 | ¥33,000~ | 相続放棄に必要な書類の収集(戸籍等収集含む)・申述書の作成・提出までサポートします。 |
| 不在者財産管理人申立 | ¥44,000〜 | |
| 遺言書の検認手続申立 | ¥33,000〜 | 家庭裁判所への検認手続申立て(書類作成含む)を行います。 |
| 成年後見人等申立書類作成 | ¥110,000〜 | 家庭裁判所への申立書類の作成・必要書類の収集を行います。 |
| 債務整理業務 | ¥44,000 着手金¥22,000 |
債権者へ連絡し、借金を免除等してもらう手続きを行います。 |
※全て税込
6.遺言・相続・信託
| 自筆証書遺言書保管サポート | ¥33,000 | 遺言とは、自分の大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。 遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効となります。自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | ¥44,000 | 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。 |
| 法定相続情報証明申請 | ¥11,000 | 管轄法務局へ申請し、法定相続情報一覧図を取得いたします。 |
| 相続人調査・関係図作成 | ¥33,000~ | |
| 遺産分割協議書作成 | ¥33,000〜 | 相続が発生しその相続人が2人以上いる場合、特に遺言等が無ければ被相続人の相続財産(積極財産及び消極財産の全て)は相続人全員の共有に属し、相続人全員が参加する協議でそれぞれ分割することができます。その分割内容を記載し、相続人全員が署名し実印を押印した書面を遺産分割協議書と言います。 |
| 未登記家屋名義変更 | ¥16,500〜 | 法務局で登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、市区町村の資産税担当課に届け出をする必要があります。 届け出をした、翌年1月1日から新しい所有者名義に変更されます。 |
| 農地法・森林法届出 | 各¥5,500~ | |
| 金融機関相続手続 | 1行 ¥22,000〜 | 遺言・遺産分割協議等に基づき預金等の払戻し及び解約を行います。 |
| 証券会社相続手続 | 1証券 ¥38,500〜 | 遺言・遺産分割協議棟に基づき有価証券及び株式の名義変更等を行います。 |
| 自動車名義変更 | ¥22,000 | 遺言・遺産分割協議棟に基づき自動車の名義変更等を行います。 |
| 家族信託設計コンサルティング | ¥275,000〜 | 信頼できる家族に財産管理を託すことにより認知症等のリスクに備えることが可能となります。 |
※全て税込
7.ドローン業務
| ドローン測量・図面作成 | ¥110,000〜 | ドローンからの映像と測量機械を併用して測量を行います。 |
|---|---|---|
| 機体登録申請 | ¥14,000 | 令和4年6月より、登録されていない100g以上のドローンを飛行させることは出来ません。国土交通省航空局への機体登録申請を行います。 |
| 飛行許可申請(包括) | ¥33,000 | ドローンを飛行させるため1年間の飛行許可を申請いたします。 |
| FISSへの予定飛行登録 | ||
| 飛行実績報告 |
※全て税込
8.その他
| 各種契約書作成 | ¥33,000〜 | 売買契約書、賃貸契約書、業務委託契約書等、各種契約書をオーダーメイドで作成いたします。 |
|---|---|---|
| 給付金・支援金申請 | ¥11,000〜 | 支援金等の代理申請を行います。 |
| 覚書等簡易証明書作成 | ¥11,000〜 | 覚書等の証明書の作成を致します。 |
| 各種相談業務 | 1時間 ¥5,000 | 遺言・相続に相談は1時間まで無料、30分までの相談は3,000円。 |
| 公正証書作成サポート | ¥22,000~ | 公証人と打合せ及び作成日における付添も行います。 |
※全て税込

一般の方向け事例
事案1:家族のためにマイホーム購入
- マイホームを建てる前に土地を購入しないといけません。不動産を購入したときは名義をかえなければならないので、所有権移転登記という手続を行います。
所有権移転登記費用:45,000円+登録免許税 - 土地を購入し、いよいよマイホーム完成。建物を建てると、建物表題登記と所有権保存登記という手続を行います。
建物表題登記・所有権保存登記費用:70,000円+20,000円+登録免許税 - マイホーム購入時にはローンを組むのが通常だと思います。その場合は金融機関との間で、土地・建物に抵当権設定登記という手続を行います。
抵当権設定登記費用:35,000円+登録免許税
※土地の住所変更登記が入る場合は追加費用10,000円 - 土地購入からマイホーム購入までの手続費用
手続費用総額: 170,000円 + 登録免許税

事例2:農地に太陽光発電を設置し売電収入ゲット
- 農地を農地以外にするには農地法の手続が必要となります。その場合は農地法4条の届出又は許可申請をすることになります。
農地法申請費用:35,000円 + 離農協力金
※農地法手続きが許可申請の場合
農地法申請費用:70,000円 + 離農協力金 - 農地法の手続が終わり、太陽光発電設備が設置されると、土地の地目を農地から雑種地に変える地目変更登記手続をすることになります。
地目変更登記費用:35,000円 - 太陽光発電における手続費用
手続費用総額: 70,000円 + 離農協力金
又は 105,000円 + 離農協力金

事案3:大切な家族のために遺言を作ろう
・遺言には大きく分けて、自分でつくる遺言と公証人というプロにつくってもらう遺言とに分かれます。
- 遺言は財産の帰属を決める大切な文書であるため要件が厳格に定められています。亡くなってから書き直すことは出来ないので、プロのサポートを受けることをお勧めします。当事務所では遺言の要件チェック・作成サポートが可能です。
自筆証書遺言作成サポート費用:20,000円 - 公証人に公正証書遺言を作成してもらうと、遺言の作成から保管まで公証人が行ってくれます。当事務所では、依頼者の意向に基づき公証人と打合せを行い、遺言作成のサポートを行います。また公正証書遺言には証人が2名必要となりますが、証人も当事務所で用意いたします。
公正証書遺言作成サポート費用:35,000円 + 公証人費用(4万円~)
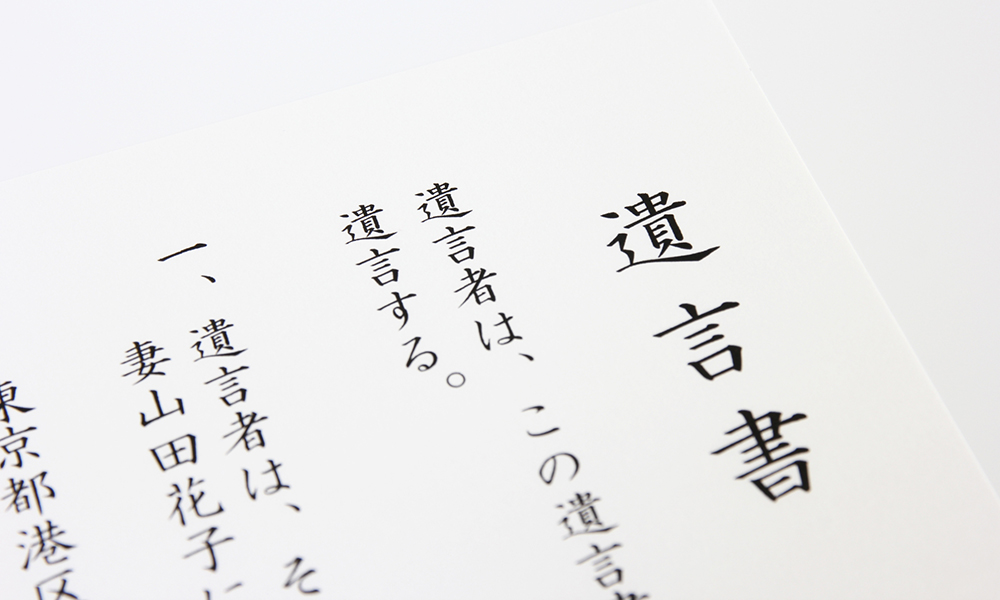
事案4:大切な父親が他界した
- 人が死亡すると相続が発生します。相続が発生した場合は原則、相続人の調査をする必要があります。また相続人調査と並行して相続財産の調査も行います。
- 次に相続財産を分割するために遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成いたします。
- 遺産分割協議の内容に従い、不動産等は相続登記にて名義変更を行います。また銀行の預貯金は相続人に払戻しを、株式については売却後、売却代金をお渡すすることができます。
- 相続についての費用
①+②までの手続の場合: 40,000円+戸籍等費用
不動産の相続登記があれば追加で30,000円~
銀行等手続があれば金融機関1行につき25,000円、
株式の売却手続があると1証券会社につき50,000円となります。
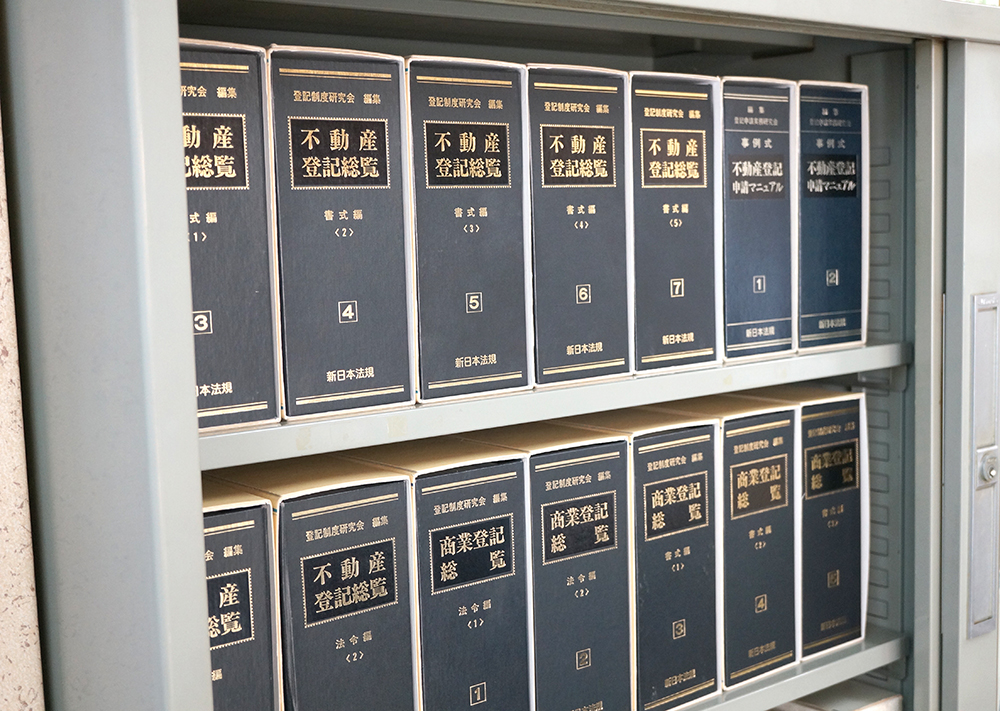
会社法人事例
事案1:株式会社を設立し、事業を大きく展開したい
- 株式会社を設立するには、公証人に定款(会社の法律)を認証してもらう必要があります。定款には必ず書かないといけない内容や書いた方が良い内容があります。依頼者の要望を聞きながら当事務所にて定款を作成、公証役場にて定款認証をしてもらいます。定款を電子定款で作成すると4万円の税金が不要になりますので、電子定款で作成いたします。
定款作成及び定款認証手続費用:50,000円+認証費用(約52,000円) - 定款が作成されると、資本金を銀行口座に振り込み、各地方法務局へ設立登記申請を行います。当事務所では登記申請時に法人の印鑑届け及び印鑑カードの受領まで行います。
会社設立登記・印鑑登録手続費用:40,000円 + 登録免許税(150,000円) - 定款認証から設立登記までの費用
手続費用総額:90,000円 + 52,000円(認証費用)+ 150,000円(免許税)

事案2:会社が大きくなり、新しく役員を選任したい
- 株式会社が新しく取締役を選任するためには株主総会を開く必要があります。株主総会で新しい取締役が選ばれると登記しなければなりません。
- ① 当事務所では役員を変更された場合は、必要書類を作成し、役員変更登記を行います。
役員変更登記費用:25,000円~ + 登録免許税

事案3:会社を引き継ぐ者がいないので、会社を閉鎖したい
- 会社を閉鎖する場合、株主総会にて解散の決議をする必要があります。解散の決議をすると法務局へ解散の登記及び清算人選任の登記をする必要があります。
- 解散の登記を行うと、債権者や債務者にそれを知らせるため通知及び官報にて公告を行います。官報公告をおこなってから2ヶ月以上何もなければ株主総会にて清算の承認決議を行います。その後、清算結了の登記を行うことにより会社は閉鎖することとなります。
- 解散から清算結了までの費用
手続費用総額:100,000円 + 免許税(41,000円)+官報(約40,000円)

